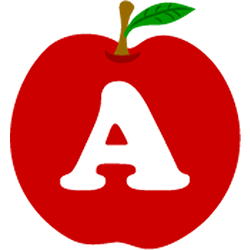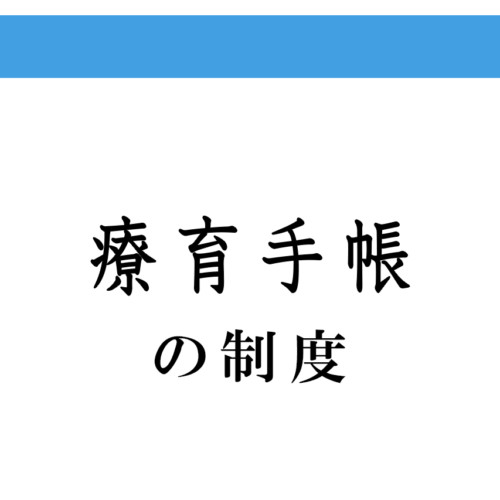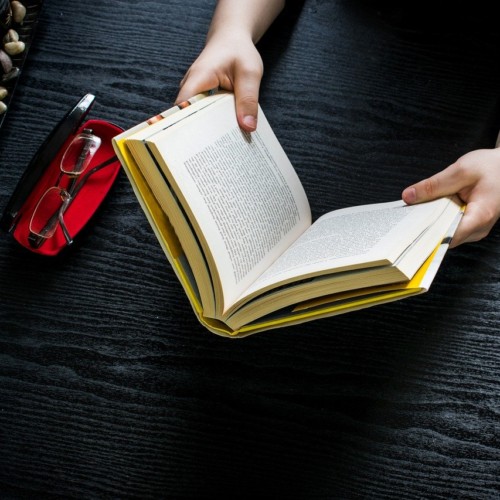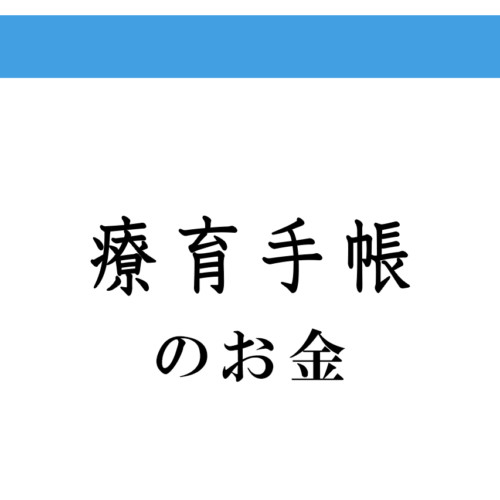気づかれない自閉症の子どもたち【一番辛いのは本人たち】

学童保育の支援員をしている方から聞いたお話をしたいと思います。
これは伝えて行かないといけないと思いました。
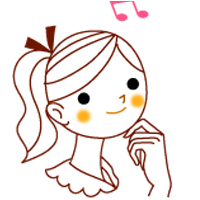
その支援員さんは、たくさんの児童と関わる中で、グレーゾーンの子どもや完全な自閉症の傾向が出ている子どもたちとも多く接する機会があるそうです。
グレーゾーンの子どもたち

普通学校に通う児童の中にはいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる、健常の子どもと発達障害の子どものどちらか判断がつきにくいケースの子どもがたくさんいます。
とくに幼少期はまだまだ成長段階であるために健常な子どもとの区別もつきにくい状況が多くあります。
子供の様子から
- 活発でよく動き回る子どもなのか
- 多動性症候群の子どもなのか
- 発達がただ単に遅めなのか
- 発達障害の傾向がでているのか
医師でも見分けがつきにくい時期があります。
グレーゾーンの子どもの中には、
ケースパターン
- 両親が気づいているケース
- 学校の先生が「もしかして発達障害かもしれない」と気づき始めているケース
- 周囲に全く気付かれていないケース
- 小学校の高学年から中学生になって、勉強に支障が出てくるようになってようやく「発達障害なのかも」と両親や先生が疑い始めるというケース
- 集団生活の中で、学童期以降も発達障害に気づかれずに成長してしまうケース
があります。
特に多いのが、成人してから気づかれるケースだと言います。
昔も発達障害の子どもはいたのでしょうが、以前に比べると、そういう子に意識が向くようになったのだと思います。
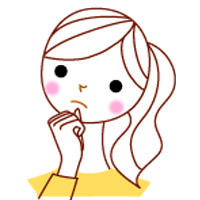
1つの学級があったら半数はグレーゾーンなのでは?という学校もあると言われているそうです。
辛い思いをするのは本人である
学校生活は規則が多く、通常の学生生活を送る中でも窮屈な思いをすることが多いのですが、発達障害や自閉症の子どもはより多くその思いを感じます。
彼らの世界にとっては正当な行動であっても、一般の学校生活では、枠を越えて好き勝手する子どもに対してはとても厳しい対応を取られてしまいます。
加えて学年があがるにつれて勉強も大変になってきて、生活面・勉強面とダブルで負担が大きくなってきます。
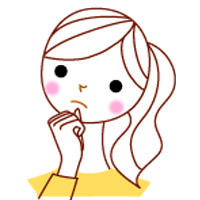
そのような環境の中で「わがままな子ども」と怒られてばっかりでは、彼らも報われない思いがどんどん募っていきます。
スポンサード サーチ
まとめ

どの子にも感情があり、それを伝える権利があります。
通常の発達をしていく児童ばかりではなく、さまざまな特性を持つ児童が通学しているのが今の学校の現状です。
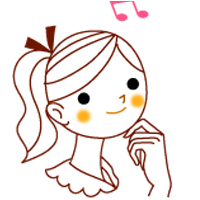
周りが思う以上にサポートを必要としている子どもはたくさんいます。
うちの子は落ち着きがないわ・・で終わらせるのでは無く、子供の将来のためにも、もしかしたらの気持ちを持って接する事も子供のためだと感じます。
そんなはずは無いと、目を背けたくなる気もちは分かりますが、一番の理解者は親しかいないのです。