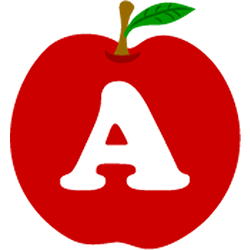自閉症児に有効な「スケジュール支援」について。その方法や注意点について。

自閉症児・者の特性として「ルーティン」というものがあります。
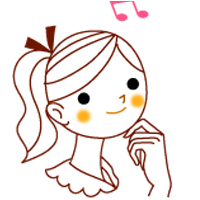
ルーティンをうまく利用すると、本人の生活リズムが整ったり心が安定してきたりします。
自閉症児・者には視覚支援はとても有効で、うちの子も1年かけて写真カードを通して意思疎通を行えるようになりました。
そこで先輩ママに視覚支援スケジュールについて聞いてみました。
同じことを繰り返すことが好き
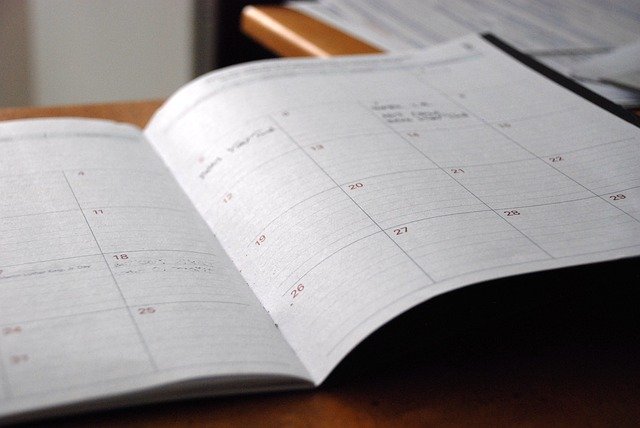
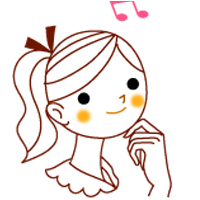
自閉症児・者は決まったことを繰り返すことが好きです。
健常な人がスケジュール手帳を持って「今日の予定」に沿って一日過ごす事があると思います。
それは予定がわかっていると安心で、逆に予定外のスケジュール変更には戸惑いを持ったりします。
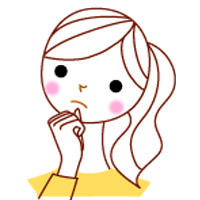
自閉症の人たちにとってもそれは何ら変わらないのです。
彼らがより安心して一日を過ごせるように支援者はスケジュールを立ててあげるサポートしていく必要があります。
スケジュール支援

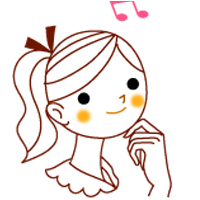
スケジュール支援とは、彼らに大まかな一日の流れを伝えていくことです。
続けていくと一日の流れが繰り返しであることンをだんだん理解してくれるようになります。
朝のスケジュールから始まり、だんだんと一日の流れのスケジュールへと広がっていくのです。
自閉症児には、視覚支援が有効

自閉症児には、視覚支援が有効なので、まずは絵カードや写真からスケジュール表を作っていきます。
いわゆる小学校の日課表のように、絵カードを使って本人の1日の流れが視覚的にわかるようにしてあげると、だんだんそのスケジュール表が現実の時間に沿っていることが分かってきます。
先輩ママの息子さんもこのスケジュール支援がとても有効だったみたいです。
スケジュール表は家庭・学校との連携で同じものを用意してもらったみたいです。
小学校1年から6年までしっかりとスケジュール支援を行っていたおかげで落ち着いた学校生活を送る事が出来たみたいです。
スポンサード サーチ
チェキが活躍

家庭ではチェキで撮った写真を絵カード代わりにして週間予定を作り、学校では日課表を同じスタイルのスケジュール表にしてもらいながら過ごします。
このスケジュール表の応用が彼らなりの「ビジネス手帳」のようになり安心して過ごせるため、気づけばだんだんと手がかからなくなってきたそうです。

予定が分かることは先の見通しが持てることで、彼らの不安は大きく解消されるので支援に取り入れてみることはオススメだと教えて頂きました。
低年齢には絵カードより実物の写真が良い

2.3歳の小さい年齢の子には絵カードは少し難しいと思います。
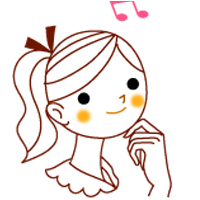
そういう時は、いきなり絵カードを作るのではなく、日ごろ見慣れている実物の写真が良いと思います。
ぴのちゃんも絵カードは理解不能ですが、自分がご飯食べてる写真や、お風呂で服を脱ぐ写真をスケジュール写真に使う事で、理解しているようです。
スポンサード サーチ
まとめ

うちの子は重度でまだ早いかなと思うご家庭でも、3歳児ころから実物写真1枚を目の付くところに貼っておき、「ここへ行こうか?」とさりげなく見せていくと、いつか写真と場所が繋がる日が来ます。
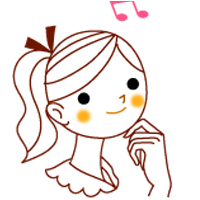
これは支援者側の根気もいりますが、玄関などに貼っておくとついでに伝える事ができるので続けやすいかなと思います。