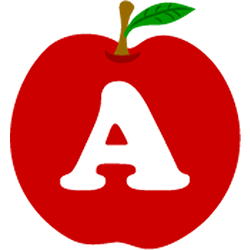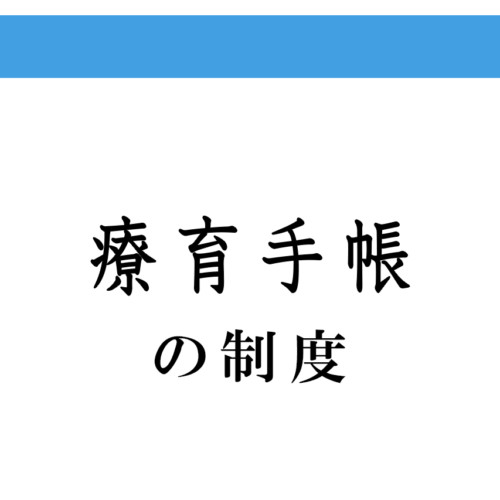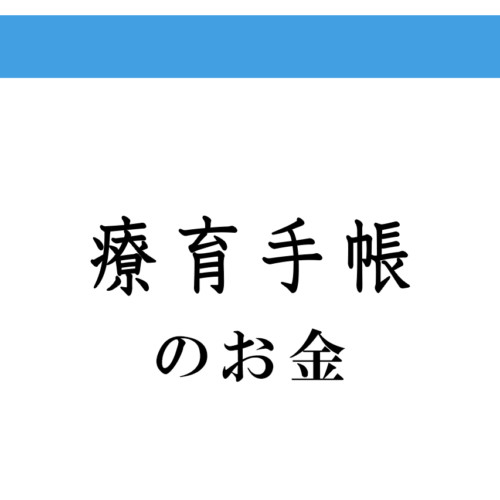発達障害・自閉症の人の危険認知力は低い!危険から守るために出来る事!

自閉症児は、どんどん興味がある方へ歩いて行ってしまいます。
歩けたばかりならまだそこまで行動範囲も広くないですが、年齢が上がるにつて、色々な物にも興味が沸いてきます。
また束縛を嫌い、手をつなぐことも嫌がる子が多いです。
しかしそのまま好きにさせていたら危険とは常に隣り合わせです。
交通ルールを教えようと思っても、知的に遅れのある自閉症児の場合は「危険」という概念が伝わりにくいです。
自閉症の人がけがをして死亡してしまうリスクは、一般の人に比べると3倍程度と言われ、幼少期はそのリスクが40倍とも言われています。
しっかりと守ってあげるには、親や支援する側の見守りがとても大切なのです。
この記事の目次
危険がわからない
自閉症児は、衝動性も持ち合わせています。
幼少期に多動傾向が強い自閉症児は、より衝動性が強く自宅からでも目を離すと居なくなってしまうこともあります。
本人にとって興味があるものはその場に行って確かめたくなるので、目的の対象物まで一直線です。
例えば、保育園などで過ごす中、電車の音が聞こえてきて、電車を見に行くために園を抜け出して脱走してしまうという事が普通にありえるのです。
途中どんなに車が多いところを通らなくてはならなくても、目的の場所までは興奮状態で進んでいくのです。

このような命にかかわる危険と隣り合わせなのですが、幼い時期は危険を伝えることが困難です。
まず親、支援側、預かり側は目を離さないようにすることが第一で、周りが危険を回避させる方法を考えていく必要があります。
年齢が上がると、成長の度合いと共に多動傾向が落ち着いてくる子も多くなります。
また危険認知力がついてくる部分もあります。それまでは常に家族や誰かが付き添って、「自閉症児を一人きりにしない」ということも大切です。
危険な玩具で遊ぶ時は注意する
先輩ママの息子さんが3歳のころ、新体操のリボンのおもちゃで遊んでいる時に、持ち手の棒の部分が喉に刺さり大変な思いをしたと聞きました。
静かに遊んでいると思ったらいきなり泣き出し、気づいた時には喉に刺さって泣いていたそうです。親子で泣きながらの救急病院へ駆け込んだと教えてくれました。
自閉症や発達障害の子どもが遊んでいる時に、長い棒のおもちゃや箸が喉に突き刺さってしまい病院に搬送されるケースも結構あるそうです。
少しでも危険な玩具で遊ぶ時は、親が目を離さないというのは鉄則です。
また家の中でも、棚の中に上って落ちてしまう、テレビを倒してしまう、テレビの液晶を叩いて割ってしまう等、予期せぬ行為をしてしまうこともあります。
親が目を離さないようにしながら、長いスパンで根気強く危険なことをしないように教えていく必要があります。
スポンサード サーチ
まとめ

この様に健常児ではあり得ない事が多々起こるのも自閉症児の特徴なのかなと思います。
2歳半を過ぎたぴのちゃんは危険認知度ゼロといっても過言ではありません。
崖も躊躇なく飛び込もうとするし、道路と歩道の違いも分かっていないです。
目を離すと直ぐに危険な目に合う事が分かります。