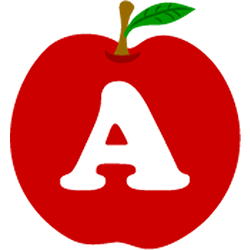妹が発達障害・自閉症のきょうだい児(お兄ちゃん・お姉ちゃん)は良い子が多いのが危険

自閉症の子どもを育てていくのは本当に大変です。
しかしそのきょうだい児は、親とは違った視点で自閉症の子どもを見て育ちます。
兄・姉・弟・妹とそれぞれ立場は違っても、自閉症のきょうだいとして生きるということは、健常の子どもの中で育つ子どもとは全く違うタイムラインとなります。
健常の人のみが暮らす家庭とは、経験することがすべて違うのです。
きょうだい児とは、自閉症の子どもにとっては良くも悪くも一番身近な存在です。
きょうだい児には親にはわからない感情がたくさんあります。
上が健常児で弟・妹が自閉症の場合

上の子どもはきょうだいが生まれてくるまでは、自分が母親を独占できていた時期があります。
それがある時とつぜん出産のために母親と離れる時期が来て、次に対面する時には母親は小さい子どもを抱いているのです。
そしてその子どもを可愛がっており、その子を「あなたも可愛がってあげてね」というようなことを言われるのです。
母親との対面もままならないまま、自分が「1番の存在ではない」という状況になったことがわかり多少混乱しますが、受け入れていきます。
ここからサバイバルの問題が始まるわけですが、その子が障害を持った子で合った場合はそこから生活も一変してしまいます。
自閉症の子育ては別体験
上の子が健常児だった場合は、自分の経験した子育ての仕方がまったく適応できないため母親も混乱します。
上の子と比べて出来ないことも多く、発達のすべてに違いがあります。自分が経験したこととは違うことだらけでパニックにもなりますし、幼少期はさらに大変です。
そしてまだまだきょうだい児も幼児の場合があります。
母親は子育て・家事・療育とたくさんのことをこなしていかねばならず一気に大変になるのですが、その母親のフォローをたくさんするのもきょうだい児であったりします。
きょうだい児は自然にいい子になり、母親の癒しの存在となる子も多いのです。
スポンサード サーチ
「いい子」が多い
自閉症のきょうだいを持つ上の子は、一般的に見て「いい子」が多いです。とてもよく周りを見ていますし、いわゆる空気の読める子どもが多いです。
ですが、その裏にはたくさんの見えない「我慢」があります。
たくさん我慢している子は、そのまま気持ちを押し込めて生きているうちにいつか気持ちの限界が来ます。
適度に発散させてあげる必要もありますし、まずきょうだいが生まれてきたところまで遡り、愛情をたくさんかけるつもりで接することも大切です。
ぴのちゃんのお姉ちゃんのケース
うちのお姉ちゃんは典型的な良い子です。
ぴのちゃんが出来ない事が沢山ある事を理解しており、先回りして色々な事を手助けしてあげています。
私としては本当にいつも助かっていますし、それに甘え切っていました。
療育もお姉ちゃんが色々手伝ってくれ、順調に進みました。
療育を始めて1か月した頃、お姉ちゃんが突然大泣きして止まりませんでした。
そのまま疲れて寝てしまいました。
完全に我慢の限界がやってきたのです。
次の日じっくり話を聞くと、「私もママを独り占めしたい」と言いました。
そんな事思っていたなんて思っていませんでした。
なるべくお姉ちゃんの相手もするようにしていたのですが、療育を始めてからはどうしてもぴのちゃんに費やす時間が多くなっていたのも事実です。
本当に色々反省しました。
それでお姉ちゃんと決めたことがあり、1か月に1度2人きりでデートする事にしました。
お姉ちゃんにもその話をしたらしっかり理解してくれました。もう5歳なのでちゃんと話も出来て本当に良かったと思います。
それからは基本的に落ち着いています。
ぴのちゃんに嫌がらせする事もなく、普段通り面倒も見てくれています。
でも私はそれに甘えず、しっかりお姉ちゃんのケアもしていきたいと思います。
お姉ちゃんいつもありがとう!感謝!