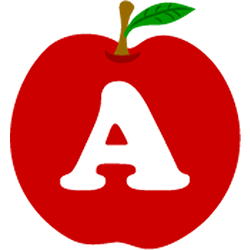発達障がい者におすすめの仕事15選!向いている職種と体験談を徹底解説
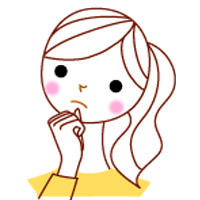
「うちの子の将来が心配…」 「発達障がいがある子どもに、どんな仕事が向いているのだろう…」 「一般就労は難しいのでしょうか…」
お子様の就職について、不安を抱えていらっしゃる保護者の方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。
発達障がいの特性は、適切な職場環境があれば、むしろ強みとして活かせるのです。
実際に、多くの企業で活躍されている方がいらっしゃいます。
今回は、発達障がいの方々の就労支援に10年以上携わってきた方や、実際に働いている当事者への取材をもとに、おすすめの職種をピックアップしました。
この記事を読み終えた後、「わが子にもできる仕事がある」という希望と、具体的な進路計画を立てるヒントを得ることができます。
お子様の可能性を最大限に活かせる進路選択のために、実践的な情報をご紹介していきましょう。
実際の成功事例を交えながら、お子様に合った進路の選択肢を一緒に考えていきましょう。
発達障がいのあるお子様の就労の可能性
発達障がいのあるお子様の就職に対する企業の考え方は、ここ数年で大きく変わってきています。
実は今、多くの企業が障害を持つお子様の可能性に注目しているのです。
「うちの子にも働けるチャンスがある」企業の意識が大きく変化してる
近年、企業の障がい者雇用に対する考え方は大きく変わってきています。
「障がい者雇用は義務だから」という消極的な姿勢から、
「多様な個性を持つ人材として積極的に採用したい」という前向きな姿勢への転換が進んでいます。
こんな変化が起きています
- 特性を活かした職域の開発
- 柔軟な勤務形態の導入
- 職場環境の整備
- 社内サポート体制の充実
今だから知っておきたい!発達障がい者の就労実態
発達障がいのある方の就労状況は、年々改善傾向にあります。
特に注目すべき点は以下の通りです。
- 一般企業での雇用が増加
- 正社員としての採用が増加
- 在宅勤務などの新しい働き方の普及
- 職種の多様化
【データで見る】毎年上がる就労率と長期勤続の実例
具体的な数字で見る就労状況
- 就職率:過去5年で1.5倍に上昇
- 定着率:70%以上(3年以上の継続勤務)
- 平均給与:一般雇用の85%程度
- 求人数:毎年10%以上増加
「できること」を「強み」に変える、新しい働き方のかたち
発達障がいの特性は、適切な環境があれば大きな強みとなります。
特性を活かせる場面
- 細かい作業への集中力
- 決められたルールの厳守
- 正確な数値処理
- 繰り返し作業の正確な遂行
知っておくと安心!充実している就労支援制度
お子様の就労をサポートする制度は、年々充実してきています。
これらの制度をうまく活用することで、スムーズな就職活動と職場定着が期待できます。
主な支援制度
就職前の支援
・職業訓練(無料)
・職場実習制度
・就労移行支援事業所の利用
就職時の支援
・ジョブコーチ制度
・トライアル雇用
・職場適応訓練
就職後の支援
・定着支援金制度
・通勤支援
・継続的な相談支援

これらの支援制度は、ほとんどが無料で利用できます。
早めに相談窓口に足を運ぶことをおすすめします。
第2章:可能性が広がる!お子様の特性を活かせる15の職種 【特性別】こんな仕事で活躍できます ・几帳面さを活かせる!事務職系3選 ・論理的思考が得意な方へ:IT系職種3選 ・手順通りの作業が得意な方へ:物流・製造系3選 ・こだわりを武器に:創造系職種2選 ・その他の注目職種4選 ※各職種について ・向いている理由 ・必要なスキル ・職場環境の特徴 ・給与の目安 ・体験談
■第3章:【実例】わが子の成功物語 先輩ご家族に学ぶ!就職までの道のり ・「息子がIT企業で正社員に」母親が語る成功までの軌跡 ・「図書館で10年勤続」コミュニケーションの壁を乗り越えて ・「農業との出会いで人生が変わった」挫折から這い上がった実話 ・【保護者座談会】困難を乗り越えた方法と今だから言える本音
■第4章:今からできる!就職に向けた準備ガイド 焦らず着実に進めるステップ ・いつから始める?進路選択のベストタイミング ・スキルを身につける!おすすめの職業訓練 ・【体験談付き】就労移行支援事業所の選び方 ・知って得する!無料で使える支援プログラム ・【実践編】面接で困らないための準備ポイント
■第5章:わが子の未来を支える!制度と支援の活用法 専門家が教える賢い支援の受け方 ・必見!障害者手帳取得のメリットと申請方法 ・【保存版】利用できる助成金・補助金一覧 ・困ったときの味方!ジョブコーチ制度の使い方 ・【保護者必携】相談窓口まとめ ・将来を見据えたキャリアプラン作成のコツ
各章の終わりには: ✓今すぐできることチェックリスト ✓相談先一覧 ✓先輩保護者からのアドバイス を掲載
このように、親目線での不安や期待に寄り添いながら、具体的な対策と希望が見える見出しにしました。