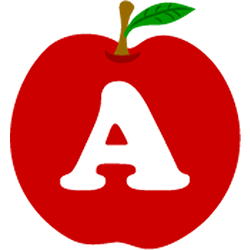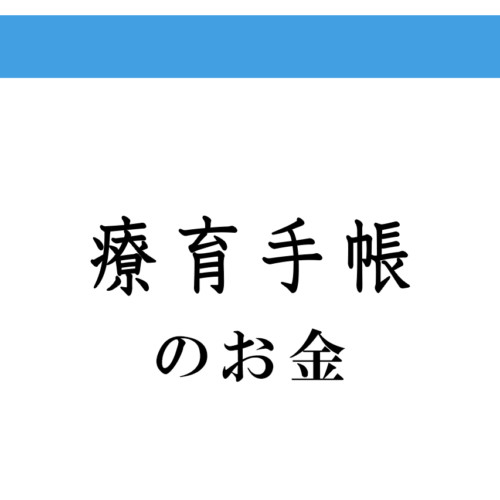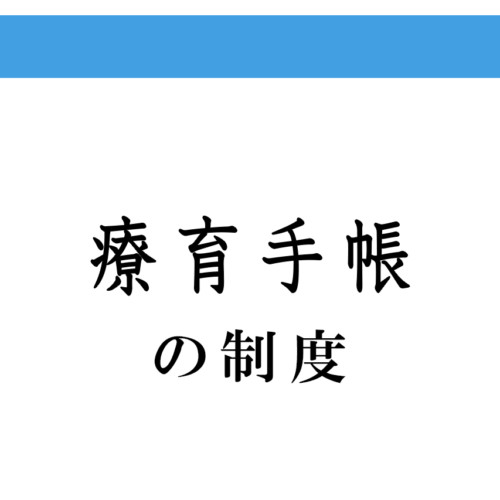自閉症児に有効な療育ABA(応用行動分析)。ぴのちゃんも受け始めました。

最近ぴのちゃんは、発達障害の専門学科がある大学で、応用行動分析(ABA)を受けています。
まだ始まって2回ですが、ぴのちゃんはとても楽しそうです。
また、新たに出来る事が増えてびっくりしています。
家でも出来るABAについても教えてもらいました。
その事について書きたいと思います。
応用行動分析(ABA)とは?
①問題の原因を環境側に求める
障がいにまつわる問題の原因を子供自身に求めるのではなく、 子供を取り巻く環境に求めることで解決を図ろうというヒューマニティックな視点を持っています。
発達障害を抱える子供は、定型発達の子供に比べて周囲の環境を理解し、 そこから自然に学ぶという点に困難を抱えるため、環境側の刺激を操作する事で子供の学習を促進する事を目指します。
②悪い行動には注目せず、良い行動を増やす
出来ない行動や不適切な行動を変える事に重点を置くのではなく、 子供が出来る適切な行動を増やしていくことで、相対的に不適切な行動を減らしていくという方法を取ります。
通常の対応では、適切な正しい行動は当たり前のこととして注目を得ず、悪い行動ばかりが注目され、 叱られるなどの働きかけを得がちです。
しかし発達障害を抱える子供は、適切な行動のレパートリーが少ないため、 不適切な行動にばかり注目し叱ってもどうしていいか分からず、改善するのが困難です。 そこで、今出来る適切な行動に着目し、そこに働きかけ広げていくことで、相対的に不適切な行動を減らしていきます。
この2点を使った療育です。
要するに、子供ができた事に対して、一緒に大きなリアクションで、ボディタッチをしながら喜ぶという事を増やしていきます。
自閉症の子は、「これをすると大好きな人が一緒になって喜んでくれる」と理解していきます。
この気持ちにさせる事がとても重要だと教えて頂きました。
応用行動分析(ABA)は家庭で出来るのか?
もちろん出来るのですが、先生に言われたのは、専門科や著書からしっかり知識を得てから行うようにした方が良いという事です。
また専門家にお子様を見て貰い、その子に合った療育を行う事が大切だそうです。
嫌な事や苦手な事をやり続けてもお子様も親御さんも疲れてしまい、続きません。
お互いに楽しい!と思える事を見つけて、楽しくできる事が大切だそうです。
スポンサード サーチ
ぴのちゃんの応用行動分析(ABA)とは

1回目は、3人の先生方とぴのちゃんが触れ合って仲良くなる日でした。
その時間で、これからのプログラムやスケジュールを立てるとの事でした。
そして、応用行動分析(ABA)で療育を行っていく事になりました。
1回目の触れ合いで、ぴのちゃんが嬉しい事や楽しい事をしたときに、ふと目を合わせたり、笑う事が多い事から、応用行動分析(ABA)が有効と言われました。
自閉症に同じ症状はありません。その子に合った正しい療育を行う事で、これからが大きく変わるとの事です。