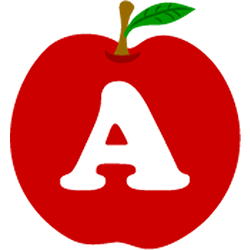発達障害・自閉症児のきょうだい児の不安や責任について

親には「自分のうちにだけ障害児が居る」や「なぜ自分のところに障害がある子どもが生まれたのか」という思いを乗り越える時期が必ずあります。
しかしそれは「障害のある子どもをしっかり育てていく」という子育ての覚悟を決める時期でもあります。
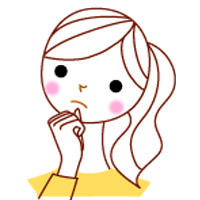
しかし、きょうだい児には、ある意味しなくても良い苦労をさせてしまうものがあるのです。
みんなのおうちには自閉症の子が居ない?!
きょうだい児の多くは、友達の家に遊びに行った時に、自分のきょうだいのような子どもが居ないことに驚くそうです。
きょうだい児の子に話を聞いてみると、幼い頃は「どこの家庭にも自分のきょうだいのような自閉症の子が居る」という概念で生きてきて、成長して友達との交流が始まり、友達の家に遊びに行った時にまず「自分のきょうだいのような自閉症の人が居ない!」と驚きます。
または保育園で気づく事が多いです。
そこからだんだんと「自分の家はほかの家と違うのだ」ということに気づき始めるのです。
漠然とした不安と見えない責任

小さい頃より、きょうだい児には漠然とした不安があります。
例えばきょうだいだけでお留守番をする機会があったとすれば、きょうだい児は上下に関わらず責任を感じてしまいます。
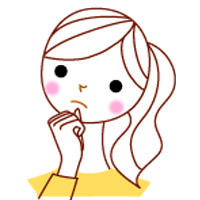
「この子の面倒を見なければ」という思いは、健常の子どもの中だけで育つ子どもよりもはるかに強いです。
それは成長していく中でも変わらず、思春期になれば障害のあるきょうだいのことをうとましく思ってしまうことや、残念に思う気持ちも出てきます。
これらの思いは通常の発達では当然出てくることです。
親としては、「障害のあるきょうだいが居るということは、結婚に影響しないのか」という思いはずっとあるのではないでしょうか。
これはきょうだい児本人にもずっと降りかかるプレッシャーでもあります。
これらは、経験してきたきょうだい児の人の話を聞けるチャンスがあれば、とても励みになると思います。
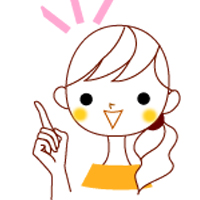
きょうだい児の見えない部分での心の負担を軽くできるように、きょうだい児もしかるべき支援を受ける必要があると強く思います。
スポンサード サーチ
まとめ
自閉症児・者の裏で、たくさんの見えない我慢と家族のフォローをしているきょうだい児。

彼ら彼女たちの心の成長を妨げないように、たくさんの愛情を注いであげるのは親の重要な役割です。
また、心を開いて話せる相手が家族以外に居ること、同じ環境で育ったきょうだい児との交流が出来る機会があれば一度参加を促してみるのもオススメです。
最近では、きょうだい児の会は増えてきました。
一度お住まいの自治体で行われていないかなど、こども家庭センターや、療育施設で聞いてみると良いと思います。

それでも見つからなければ、ご自身が中心となって、自閉症児のいるお母さん方へ呼びかけ、開催するのも一つだと思います。
ぴのちゃんのために療育へ行ったり、保健センターへ行ったりと動いている分、きょうだい児(ぴのちゃんのお姉ちゃん)のためにも同じくらい動いてあげたいなと思います。