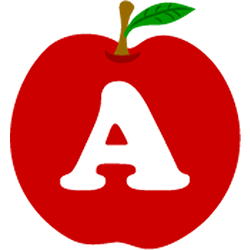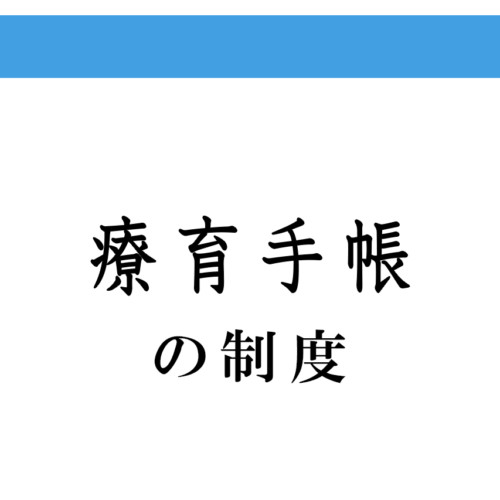発達障害や自閉症の子供たちに世界で広がっている有効な音楽療法。日本は遅れているわけとは。

発達障害のある子どもの療育に、「音楽療法」を取り入れる動きが世界では広がっています。
まだ日本では音楽療法の保険適用や法整備が実現されておらず、音楽療法士の資格も国家資格となっていないため、療育としての普及には多くの壁が存在しています。
「音楽」は「言葉」と異なり、「感じるもの」という側面が大きく、子どもの心にダイレクトに訴えかけることができます。

「始めと終わりがはっきりしているため見通しが立てやすい」
「繰り返しがある」
等、自閉傾向の強い子どもが好む構造になっているのも特徴です。
そして、楽器を使うことにより、子どもは五感が刺激され、感覚統合訓練の役割も果たしてくれるのです。
なにより、子どもたちは、このように音楽を通してコミュニケーションを学び、社会性を獲得していけるのです。
日本で唯一、医療現場での音楽療法を取り入れているクリニック
筑波こどものこころクリニックの院長、医学博士の鈴木直光先生という方が率先して音楽療法を取り入れた療育を行っているそうです。
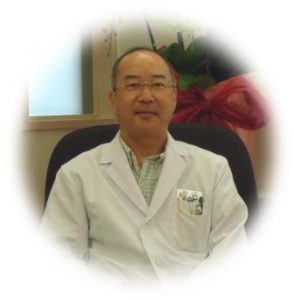
先生曰く、音楽療法は、言語的な発達、衝動性の抑制、社会性の伸びなど、広い範囲の発達を促すことができると言います。
発達障害児/者の音楽療法は個々で違うのでオーダーメードが必要です。
全ての発達障害や自閉症に同じ音楽に効果があるという分けではなく、それぞれの度合いや症状、性格によって好みの音楽や、リズムが違うと言います。
海外では、その個々に合わせて音楽を提供するための国家資格をもった音楽療法士がいるのです。
指示が聞けるかどうかでも、変わってきます。
実際の音楽療法の方法
選曲も自閉症児にわかりやすいメロディー、リズムの曲がちゃんと考えられており、頭に残りやすく、自分からセッションに加わりやすいメロディーになっています。
主に使う楽器はハンドドラム、太鼓、ハンドベルなど、自分で簡単に音が鳴らせる楽器が選ばれます。
歌、ダンス、リズム遊びと楽しみながら、太鼓でリズムを取ることを覚えていきます。
太鼓やドラムの音は「叩くと音が鳴る」というように、自分でアクションを取ると必ず反応があります。
自分で音を鳴らすことがすぐ耳に反映されるために興味を持ちやすかったり、「もっと叩いてみよう」という意欲にもつながっていきます。
さらに、太鼓の音はサウンドヒーリングの観点からも、おなかに響いてに気持ちが安定してくると言われています。
他国でも、ハンドドラムの音はとても癒しの効果があるとして、世界中で人気の楽器です。

音楽療法の時間の中で、太鼓をたたくことを何度か繰り返しているうちに、タイミングがだんだんと曲の拍数に合わせて叩けるようになったり、曲に合わせて自分からリズムを取れるようになってきます。
スポンサード サーチ
音楽療法の課題
進行をしながら指導する人・自閉症者に寄り添う人・準備をする人とサポート体制も万全でないといけません。
多動傾向のないお子さんでしたら、マンツーマンの指導でも可能かもしれません。
超多動傾向の自閉症児1人に対して3人の指導者が必要な事もあります。
また可能な場合は、母親が「自閉症者に寄り添う人」として参加するのがベストだと思います。
なにより、日本には音楽療法が行える施設や医療機関がとても少ないです。
この専門知識を持った人も同様です。
自閉症患者が増え続ける現代で、こういうところにも目を向けて、改善をしてほしいものです。
まとめ
音楽のセッションはハートからのコミュニケーションにつながるため、療法士とセッションすると、笑顔が増えると言われます。
音楽とは音を楽しむこと、喜びの中でできる療育としてとてもおすすめです。
また、才能を伸ばしてくれる思わぬきっかけになると思います。
それが将来のお仕事へのきっかけになるかもしれません。